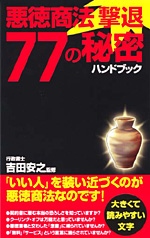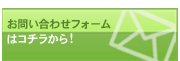マルチ商法とは?

■マルチ商法とは?
クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは若者にはびこるマルチ商法をご紹介します。
■マルチ商法とはどういうものか?
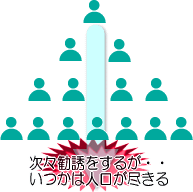 マルチ商法とは最近では[MLM〜マルチレベルマーケティングプラン]という略称で呼ばれることもありますが、詳しくはこのMLMの一種の形態です。もっと厳密にいえば正しい定義は非常に難しく、日々流動的に変化していく販売形態を漠然と大きな枠組みで規定しているに過ぎません。
マルチ商法とは最近では[MLM〜マルチレベルマーケティングプラン]という略称で呼ばれることもありますが、詳しくはこのMLMの一種の形態です。もっと厳密にいえば正しい定義は非常に難しく、日々流動的に変化していく販売形態を漠然と大きな枠組みで規定しているに過ぎません。
一応消費者(無店舗個人)が一定の金銭的負担を条件に商品の販売や役務の提供に係わるビジネスに参加するピラミッド式の販売方法を広くこのようにいうことがおおいです。
■特定商取引法(旧訪問販売法)上での連鎖販売取引(マルチ規制)
マルチ=法律違反の悪質なもの
という考えをもたれている方も多いと思いますが一般的な商行為においてもこれらに類似する商売形態が多々存在いたします。ですから100%悪質というわけではありません。
しかし、一般個人がターゲットになることから知識も判断力もなくただ、利益があがるとの言葉で巧みに誘われ多額の被害を出すというのも多発しました。その結果昭和51年に「訪問販売等に関する法律」にて「連鎖販売取引」として規制を受け、昭和63年には法改正によってさらに規制範囲が拡げられました。さらに平成14年には「特定商取引に関する法律」としてさらに強い規制がかけられております。 その後も度重なる改正法でその都度規制が強められております。
特定商取引法上にて「クーリングオフ」が可能とされる条件は以下の4つのすべてを満たす必要があります。
1)物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)の販売(販売の斡旋を含む)事業又は有償でおこなう役務の提供(提供のあっせんを含む)事業であること。
2)その物品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者または同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんをする者を勧誘すること。
3)「特定利益」を収受しうることをもって勧誘すること。
4)「特定負担」をすることが取引の条件になっていること。
これらの条件を満たす業者や消費者は「契約書面」の交付義務、クーリングオフの記載、通知義務、20日間のクーリングオフ等のいわゆる特定商取引法上の消費者保護や業者規制が適用されます。
■特定商取引法改正による返品ルールとは?
平成16年の11月11日より新たなマルチ商法規制が始まりました。その中でも特徴的なのは「90日間の返品ルール」というものになるでしょう。
実はそれまではクーリングオフ経過後の特定負担商品の返品は非常に難しいという現実問題がありました。
一度手に入れたマージンをなくしたくは無いというマルチ信者達の心理状態では返品返金に応じるということには事実上なりにくかったという頃が主な理由です。
そこで、法改正により強制的に返品ルールを設けたということになります。ただしいくつかの条件は付いてきます。
- 入会してから1年を経過していないもの
- 解除前90日以内に引渡し(サービス権利の場合は移転)をうけた商品(権利)であること
- 自らの責任で商品を毀損、滅失していない
- 商品を再販売、使用、消費していない(ただし販売業者や担当者が使用、消費させた場合を除く)
等になります。
これらの条件を満たせば販売価格の10分の1相当のお金で未使用部分の解約返金できるようになります。
実質的には新規入会者でなんのビジネス活動もせず商品を買っただけで使用すらしていないという方のみが対象と考えると良いでしょう。
■マルチの代表的トラブル
 マルチ商法につきもののトラブルを紹介していきます。
マルチ商法につきもののトラブルを紹介していきます。
1)人間関係
・知人や友人を勧誘することから、ビジネスの失敗が人間関係の悪化を招く
・ビジネスに熱中してしまう為、または失敗から会社を退職してしまう
2)勧誘行為について
・絶対に儲かる、月々○○万円入るなどと断定的な判断で勧誘する
・非常にしつこく何回でも勧誘してくる
・経済産業省や議員の誰々が理事だ、等の言葉で公的な期間がいかにも関与しているようにだます。
・友人、知人からその内容を告げられずに業者までつれられて契約させられる。
3)契約履行面について
・親が訪問販売であるが、実際の子の販売組織がマルチであるときに、クーリングオフを20日のところ8日と記載してしまう。
・返品制度が親の拒否等によって実際的に機能しない。
・中途解約は認めない。
4)契約解除時について
・クーリングオフ阻害行為をする
・威迫、困惑させて解約行為を妨げる(会社の上司に言うぞ。親にお金を取りにいってやる。)
・返金に応じない
■マルチ商法の体験談
![]() 経験談 : 昨日セミナーと称する大洗脳大会に行って来ました。内容は、浄水器や健康器具の販売についてのもので、はじめの1時間で商品説明、次の1時間でネットワークを広げれば、月収200万以上になるという話をされました。商品説明は全く理論に穴だらけで、聞く価値は全くありませんでしたが、ネットワーク拡大による収入についての話は、うまくできていました。
経験談 : 昨日セミナーと称する大洗脳大会に行って来ました。内容は、浄水器や健康器具の販売についてのもので、はじめの1時間で商品説明、次の1時間でネットワークを広げれば、月収200万以上になるという話をされました。商品説明は全く理論に穴だらけで、聞く価値は全くありませんでしたが、ネットワーク拡大による収入についての話は、うまくできていました。
まず、気になったのは社員の若さです。話の合間に、若い子が出て来て「まえせつ」のようなことをしていました。内容は、「このシステムを聞いて、世界が変わりました。」「同年代のみなさんも...」「生活が充実して,生きがいが...」等のように若い参加者の一体感を煽りたて、期待感を増幅させていました。
次に、音響効果を利用した会場設営です。社員が、部屋の後ろを取り囲むように立ち、何かある毎に拍手をするのです。このことで、会場全体に拍手が響き、凄く大きな拍手の渦になります。真面目そうな人達は素晴らしいことを見聞きしている気に成って行ったようで、大きくうなずきながら話を聞くようになっていました。休憩時間は、軽いノリを強要するかのように、ダンス系の今どきの音楽が大音量でなっていて、今から50万円の契約をしなければいけないと言う深刻さを感じさせないようにしているかのようでした。
やっとセミナーが終ったと、思ったら今度は個別の談話になります。僕は、既に入会している友人について行ったのですが、その友人とその上司みたいな人に囲まれました。周りで個別談話していた茶髪君達は、50万円の契約を用意されてあるローンにごまかされ、月1万5千円の契約として軽くサインして行っているようでした。まさか浄水器や肩こりの消える石が欲しいわけでも無いでしょうに。
気づくと、談話しているのは僕達のグループだけになっていました。次々に、位の高そうな人が僕に握手を求めたり、近くで腕を組んで僕の話を聞きはじめました。この集団リンチ状態で、目に見えない脅迫がされ始めます。僕の主張は「50万の契約をこの場で、即決することはできない」といったものでした。これに対して、社員達がエピソードを話して来るのですが、この話術は非常に巧みなものでした。
エピソード1:今しか無い
過去に断った奴は、2度と誘わない。今では羨ましがって、この仕事をやりたいって言ってきたけど、電話きってやりましたよ。
エピソード2:自尊心の利用
話が本当に理解できて、やらない人がいるなら、ただの根性なしとしか思えませんね。そういう人も過去に数人だけいましたけど。
エピソード3:逃げ道
確かに大金で、渋るのは分かります。でも、明日になればその分あなたにとって不利ですよ。もし、気が変わったら、クーリングオフもできますし。
エピソード4:ネームバリューの利用
今年からダイエーも参入します。来年は、TOYOTAが参入すると公式発表している商法です。アメリカでは、普通の主婦がこのようなサイドビジネスで何百万と稼いでいますし。他にも、僕に同意したり、協調したり、冗談を交えて契約を勧められました。
僕がそのセミナーに参加するきっかけとなったのは、友達からの勧誘です。なぜ、無理のある金儲けの話にみんなが喜んで大金を払おうとするのかを知りたくて、話を聞きに軽く行ったのですが、7時間もかかってしまいました。あんなもの行く時点で間違っていました。未だに疲れています。
悪徳業者 : 僕が体験談で書いたのは、ABCという会社ですが、悪徳なのかどうか分かりません。委託販売を請け負っているらしく、浄水器メーカーは「ABCDEF」とか,そういう名前でしたが...みんな嬉しそうに契約していましたから。悪質なのか,どうなんでしょう?
感想 : 実際の手口は、この通りだと感心しました。
初めてマルチを身近にかんじてから思うのですが、前もってこういうページを見ておいたらほとんどの人が、契約しないでしょう。でも、結構その場にいると、巧妙にその気にさせられるので、近付かないのが一番ですね。
■最後に〜マルチ被害にあわないために
マルチ商法はやり方によっては確かに儲けることができるものです。しかしそれは極々限られた上位の組織の人だけであってリスクが非常に大きいものです。
世の中が不況なのでこのような儲け話に飛びつきたくなる気持ちも解りますがこの世に「簡単にスグ儲かる」話はない、ということを最後に言いたいと思います。
またマルチ商法は近年ネットワークビジネスだとかMLMということに名前を変えてイメージの払拭にやっきになっておりますが結局は言葉を変えたのみで根本は同じです。
現時点で法律の規制を読みますと正当に勧誘行為や商売を行うことは不可能というくらいに強い規制がかかっています。つまりどこかしらで違法勧誘をしなければまず現実的に商法が成り立たないくらいにとんでもなく厳しい規制が有るということです。(私は日本国は実質的にマルチ商法を禁止していると思っています)
知らない内に被害者が加害者になるというものがマルチです。違法ではないのでやるなとも言えませんが少なくとも法令、道義的な義務などを理解し、守って行うことが必要ですね。純粋に守ったら勧誘行為はまずできませんが。
われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。
クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
![]() 無料メール相談フォームへ
無料メール相談フォームへ